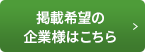【4ステップ】親の遺品整理をスムーズに進める方法(実家がスッキリ片付く)
2025.02.25

- 親の遺品整理をどこから手をつけたらいいかわからない
- 心の整理がつかず、作業がなかなかできない
- 実家を片付ける時間がなかなか取れない
こんな悩みにお答えします。
親の遺品整理は、多くの人にとって初めての体験で、戸惑いも多いものです。感情的な負担に加え、物理的な作業量の多さに圧倒されることも少なくありません。しかし、きちんとした手順で取り組めば、効率よく進めることができ、心の整理にも役立ちます。
この記事でわかることは、以下のとおりです。
- 遺品整理にまつわる基礎知識
- 遺品整理をする前にしておきたい5つのこと
- 4STEPで親の遺品整理をスムーズに進める方法
- 遺品整理で親族間に起こりがちなトラブルと対応策
- 親の遺品整理をスムーズに進めるコツと注意点
遺品整理は感情と作業の両面で大きな負担になりますが、適切な進め方を学べば前向きな気持ちで取り組めるようになります。
この機会に、悩みを解消しながら実家をスッキリ片付けてみましょう!
遺品整理とは?知っておきたい基本知識
遺品整理とは、大切な人が亡くなった後、その人の持ち物を整理する作業です。故人の思い出や生活を感じながら進めるため、心の準備がとても大切です。
親世代は、普段から物を溜め込むことが多い世代のため、思い出深い品物も多くて整理に時間がかかりがちです。また、遺品整理を行うのは相続人が中心ですので、家族間での協力も不可欠。
各家庭の状況に応じて時期や方法についても慎重に選択し、計画的かつ心の整理を並行させながら進めることが求められます。
遺品整理をするうえで、あらかじめ知っておきたいことをまとめましたので、順に見ていきましょう。
遺品整理は心の準備ができてから
遺品整理を始める前に、まずは自分の気持ちを整理する時間をしっかり持ちましょう。
なぜなら、故人との思い出が詰まった品物や生前に使っていた品物に囲まれると、整理作業が感情的に辛くなることがあるためです。無理に進めることは避け、少しずつ心の準備を整えることが肝心です。
法事や特別な日をきっかけとして、親族が集まりやすいタイミングで行うことも効果的です。お互いの気持ちを理解し合うことで、作業をスムーズに進められる環境を整えることが可能です。
心の負担を少しでも軽くするためにも、十分な準備を心掛けましょう。
遺品整理をするのは基本的には相続人
遺品整理は、基本的に故人の相続人が行うことになります。
ですので、一人で背負い込むことなく、兄弟や親戚と協力し合う姿勢が求められます。各自の役割を分担し、遺品の確認を行いながら、整理作業を進めるようにしましょう。
そうすることで作業の進捗もスムーズになり、心の支え合いにもつながります。
不要な親族間トラブルを回避するためにも勝手に遺品整理を進めることは避け、相続人を巻き込むか、相続人の合意を得たうえで遺品整理を進めるようにしましょう。
相続税は10ヶ月以内に納付する
相続税の納付時期についても押さえておきましょう。
相続税は故人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に納付しなければなりません。この期限を過ぎると、『無申告加算税』や『延滞税』などの利息が発生するため注意しましょう。
相続税の申告書を作成しなければならないため、適切な手続きを行うために専門家の助けを借りることも有効です。疑問点や不明点をクリアにしておくことで、納付までの流れが円滑に進み、結果として金銭的な負担を軽減できることも多々あります。
相続税に関する遺品整理を優先的に着手するように心がけてくださいね。
相続放棄は3ヶ月以内にする
相続で故人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続の対象になります。もしも故人の負債を引き継ぎたくない場合は、相続放棄の手続きを進める必要があります。
具体的には、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ることが原則です。
ただし、相続放棄した場合は、一切の相続権を失うため十分に理解したうえで判断するようにしましょう。遺族間で話し合いながら、慎重に進めることが求められます。
ここで肝心なのは、故人のプラスの財産とマイナスの財産をきちんと明確にしておくこと。後になってプラスの財産が見つかっても、一旦相続放棄をしてしまえば、取り返しのつかない事態につながりかねないからです。

【事前準備】遺品整理をする前にしておきたい5つのこと
遺品整理を始める前に、次の5つの事前準備をしておきましょう。
- ①遺言書・エンディングノートを探す
- ②親族間できちんと話し合う
- ③現地へ足を運んで下見をする
- ④作業スケジュールを立てる
- ⑤遺品を整理するための道具を揃える
これらの準備をきちんとしておくことで、遺品整理がスムーズに進み、後々の作業に混乱やストレスを招く可能性を下げられるからです。また、効率的かつ落ち着いて作業を進めることもできるでしょう。
計画的に進めるためにも、上記の項目をぜひ参考にしてみてください。
①遺言書・エンディングノートを探す
まず、故人の遺言書やエンディングノートの有無を確認することが大切です。
これらの書類には、大切な財産や遺品の扱いについて故人の意思が示されているからです。見つけることができれば、故人の遺品に対する意思が確認できる可能性が高いため、遺品の処分する際の参考になるからです。
また、遺族間でのトラブルを避けるためにも、これらの書類が重要な役割を果たします。なぜなら、特定の財産についての分け方などが明示されていることも多いため、話し合いがスムーズに進むきっかけとなるからです。
このように、特に相続に関係する事項が記載されている場合、今後の手続きの大きな参考にもなるでしょう。
②親族間できちんと話し合う
遺品整理を行う前に親族間での十分な話し合いが必要です。特に相続人が複数いる場合、各自の意見や希望を尊重するように心がけましょう。
整理作業の進行や分け方について話し合いを行うことで、スムーズに事が運ぶ可能性が高まります。感情的な部分に触れることもありますが、しっかりと意見を出し合うことで、トラブルを未然に防ぐための一歩を踏み出せます。
このような親族とのコミュニケーションは、スムーズに遺品整理を進めるうえで重要なツールとなるのです。
③現地へ足を運んで下見をする
実際に遺品整理を始める前に、故人が住んでいた場所を訪れて下見を行うようにしましょう。
実際に足を運んで物の量や種類、状態を把握しておくことで、どの程度の時間や労力が必要になるかを予測できるからです。
また、気付かなかったことにも気付くタイミングとなり、さまざまな角度から整理を考える手助けにもなります。物の整理をする際には、道具を取り揃える必要も出てくるため、現場の状況に合わせた準備をスムーズに進められるメリットもあります。
感情的な面でも、実際にその場所に訪れることで心の整理ができる場合もあります。いきなり遺品整理を始めるではなく、事前に下見をしておきましょう。
④作業スケジュールを立てる
遺品整理を効果的に進めるためには、作業スケジュールをしっかりと立てることが不可欠です。
どの期間にどの作業を行うかを明確にすることで、作業の効率が大幅に向上するからです。
特に、親族が集まる日などを考慮に入れて作業日程を設定することを心がけましょう。周囲の人たちとの協力が得られるタイミングを事前に確保できれば、遺品整理をスムーズに進められるからです。
また、各ステップに必要な時間を見積もることで、精神的な余裕も生まれ、安心して作業に取り組むことが可能です。
⑤遺品を整理するための道具を揃える
遺品整理をスムーズに行うためには、以下のような道具を事前に準備しておきましょう。
- 段ボール
- ガムテープ
- ゴミ袋
- 軍手
- スリッパ
- カッター・ハサミ
- ビニール紐
- マジックペン
また、家具や大型の遺品を運び出すために、場合によっては軽トラックなどの用意も必要になるでしょう。これらの道具を揃えておけば、作業が円滑に進むだけでなく、物の扱いに対する安全性も高まります。
遺品整理を始めてから「〇〇が足りない!買いに行かなくちゃ!」となれば、作業が一旦ストップしてしまい、時間のロスにつながるからです。その結果、あらかじめ決めたスケジュールが大きく崩れかねません。
可能であれば、手伝ってくれる人たちにも必要な道具を事前に共有しておくことで、効率よく整理作業を進めることができるでしょう。
【4STEP】親の遺品整理をスムーズに進める方法
親の遺品整理は、感情的にも物理的にも大変な作業です。しかし、適切な手順を踏むことで少しでもスムーズに進めることができる方法があります。
次の4つのステップをぜひ参考にしてみてください。
- 【STEP1】貴重品や重要書類を最初に探す
- 【STEP2】遺品を「残す」「処分する」の2つに仕分ける
- 【STEP3】リサイクルや売却を活用して不用品を処分する
- 【STEP4】冷蔵庫など家電を含むゴミを適切に処分する
効率的に遺品整理を進め、無駄な手間を省くためには、計画的なアプローチが求められます。
これらの具体的なステップを知っておくことで、精神的な負担を軽減し、より安心して作業が進められます。
【STEP1】貴重品や重要書類を最初に探す
遺品を整理する際の第1ステップとして、貴重品や重要書類を最優先で探しましょう。
故人の遺産に関する資料や金融機関の書類など、相続手続きに必要になる書類だからです。また、鍵や通帳、印鑑なども見落とさないように注意しましょう。
これらの品々は、遺品を整理する中で後の手続きをスムーズに進めるためのカギとなります。
探す際には、故人が普段保管していた場所を思い出しつつ、意外な場所に保管されている可能性も考慮しながら丁寧に確認を行いましょう。
【STEP2】遺品を「残す」「処分する」の2つに仕分ける
遺品整理の次のステップは、遺品を「残す」ものと「処分する」ものに分ける作業です。
この仕分けは感情的な壁に直面することも多く、特に「捨てられない」と感じる品物がある場合には慎重かつ丁寧に向き合うようにしましょう。焦らず、じっくりと時間をかけて向き合うことが大切です。
基本的には、ご自身や家族にとって思い入れがあるものや価値があると思うものを「残す」一方で、不要なものや今後使う予定のない物は「処分する」という基準を明確に設定すると仕分けがスムーズに進められます。
また、家族同士で意見を交換することで、他の人が大切に思う品物や共有の思い出と向き合う機会にもなり、より納得のいく決定を行うことができます。
感情に流されすぎず、適切な基準を持つことが、より良い遺品整理の結果につながります。
【STEP3】リサイクルや売却を活用して不用品を処分する
遺品整理をしている際に見つかる不用品は、リサイクルや売却することで、効率的に処分できます。
特に遺品整理を行う際には、まだ使える品物を無駄にせず、リサイクルショップに持ち込むことや、オンラインのフリマアプリを利用して売却する方法が便利です。また、地域のリサイクルセンターの活用も一つの選択肢であり、環境への配慮をしながら不用品を処分することが可能です。
こうしたリサイクルや売却の取り組みを活用することで、単に不要品を捨てるのではなく、より価値ある形で手放すことができます。
必要な人に不用品を届けられるとともに、売却できると金銭的にもお得に不用品を処分できます。不用品を有効に活用する機会を最大限に活かし、有意義な処分方法を選ぶようにしましょう。
【STEP4】冷蔵庫など家電を含むゴミを適切に処分する
最後に、冷蔵庫や洗濯機などの大型家電を含むゴミを適切に処分する必要があります。
- エアコン
- テレビ
- 洗濯機・乾燥機
- 冷蔵庫・冷凍庫
などの家電4品目や、パソコン・スマホなどの小型家電は、法律に沿った適切な処分が求められますので注意が必要です。
多くの自治体では、家電リサイクルの手続きが案内されており、指定された業者や家電量販店などで処分をしなければなりません。これにより法律に則った適切な処分が行え、環境への負担も軽減できます。
特に大型のアイテムは運び出しも大変ですので、事前にスケジュールを立てておくことで効率的に行動を進めることができるでしょう。

遺品整理で親族間に起こりがちなトラブルと対応策
遺品整理においては、感情的な要素が絡むため、親族間でのトラブルが発生することがあります。
遺品に対する思いは人それぞれ異なり、相続人同士の意見がぶつかることが多いからです。
このようなトラブルは、適切な対応によって解消や予防が可能です。まず考慮すべき点や対策を知ることで、よりスムーズな遺品整理を実現できるでしょう。
親族から遺品を譲ってほしいと言われた場合の対処法
親族から遺品を譲ってほしいと求められる場面では、感情が揺れ動くことが多々あるでしょう。
このような場合、まずは冷静に受け入れ、親族の意見を理解する姿勢が重要です。譲渡に応じるかどうかは、遺品の価値や思い入れ、相続に関する取り決めを考慮して判断する必要があります。
また、譲渡する場合には、事前に他の相続人と相談し、意見を集約しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
相手の気持ちに配慮しつつ、自分自身の考えも伝えるよう心掛けておけば、良好な関係を保ちながら整理作業を進められます。
人形や仏壇など処分に戸惑うものの扱い方
遺品整理を行う中で、人形や仏壇といった特別な意味合いを持つ品物は、捨てられないと感じる方が多くいます。
なぜなら、これらの品物には故人の思い出が深く刻まれているため、処分に関する決断が難しくなりやすいからです。
このような場合には、まず家族で話し合いの時間を持つことが大切です。それぞれの共有する思い出や感情を理解し合いながら、どうするべきか意見を出し合うことで、納得できる結論へたどり着きやすくなります。
また、処分以外にも寄付や保管といった様々な選択肢を検討することが必要です。どうしても捨てられないと感じる場合には、寺社や信頼できる専門業者に相談して供養を行った後に適切に処分する方法もあります。
最終的に誰がどのように扱うかを決め、対応策を明確にすることで、感情的な負担を軽減しスムーズな進行が可能となります。
どうしても遺品整理が進まない場合の解決策
遺品整理が進まない場合、心理的な負担や体力的な疲労が原因であることも多くあります。
心の整理がつかず、前に進められないときは、無理をせず段階的に進めることが大切です。
ただ、自分一人では進められない場合もあるため、専門の業者に依頼するのも選択肢の一つです。トラブルを未然に防ぐために、一度相談してみることで第三者の視点も得られ、具体的なアクションプランが得られる可能性があります。
また、時間を区切って少しずつ整理する方法も効率的です。普段の生活に支障をきたさない範囲で進めることで、無理なく遺品整理を行うことができるでしょう。
親の遺品整理をスムーズに進めるコツと注意点
親の遺品整理では、感情的な負担が伴い、思うように進まない場合も多々あるでしょう。
スムーズに進めるためには、計画的なアプローチと仲間との協力が重要です。
ここでは、実践的なポイントや注意すべき事項について考えます。これらを意識することで、遺品整理がより効率的に進む可能性が高まります。
親族を巻き込んで一緒に遺品整理する
親族と一緒に遺品整理を行うことで、個々の思いを共有しながら進められるメリットがあります。
複数人で作業を行うことにより、物の仕分けや判断が早まり、心の負担も軽減されるでしょう。また、それぞれの思い入れがある物に対して意見を交わすことで、決断がより納得のいくものとなりやすいです。
全員が参加することで、共有の思い出について話し合うきっかけにもなります。
親族同士のコミュニケーションが深まることで、整理の過程そのものも価値ある時間となることが期待されます。
ロック解除やパスワード解除できない遺品は業者に依頼する
遺品整理を進める中で、スマートフォンやパソコンといったデジタル機器のロック解除やパスワード解除が必要になる場合があります。
このような場合、自己流での解決は難しいことも少なくありません。そんなときは、専門の業者に依頼することで、安心して作業を進めることができます。データ復旧やプライバシーの保護も考慮されており、的確な手続きが行われるため、非常に安心感があります。
特に貴重なデータや思い出を保存したい場合は、専門家の力を借りることが現実的な選択肢と言えるでしょう。
思い切って遺品整理業者の力を借りる
遺品整理が思うように進まない場合、思い切って業者の力を借りてみましょう。
専門業者は豊富な経験を持っており、迅速かつ適切な対応を行えるからです。自分たちでは時間や手間がかかる作業も、短期間で効率良く進めてもらえるのは大きな安心感も得られます。時間に余裕がない方や、遠方に住んでいる方にとっても利便性の高いサービスと言えるでそう。
また、業者に依頼することで、物の処分や運搬といった物理的な労力から解放されるため、精神的な負担も減少します。
遺品整理業者に依頼するときは、費用やサービス内容を比較したうえで、自分たちに合った業者を選ぶことが重要です。相見積もりを取って費用相場を確認しつつ、口コミや実績も比較検討するようにしましょう。
信頼できる遺品整理業者より適切なサポートを受けられれば、遺品整理という大変な作業をよりスムーズに進めることができます。
まとめ
今回は親の遺品整理について解説しました。
感情面と実務面が複雑に絡み合う遺品整理ですが、あらかじめ計画を立て、準備を整えることでスムーズに進めることが可能になります。親族や家族を巻き込むことで、負担を軽減しながら整理の理解も深められます。
遺品整理をする前には、以下の準備がおすすめです。
- ①遺言書・エンディングノートを探す
- ②親族間できちんと話し合う
- ③現地へ足を運んで下見をする
- ④作業スケジュールを立てる
- ⑤遺品を整理するための道具を揃える
そのうえで、遺品整理は次の4STEPで進めてみてください。
- 【STEP1】貴重品や重要書類を最初に探す
- 【STEP2】遺品を「残す」「処分する」の2つに仕分ける
- 【STEP3】リサイクルや売却を活用して不用品を処分する
- 【STEP4】冷蔵庫など家電を含むゴミを適切に処分する
なお、どうしても自分たちだけでは進められないと感じた場合は、専門業者の利用も一つの選択肢です。これらのサポートをうまく活用することで心身にゆとりを持ちながら整理を進められるでしょう。
遺品整理の過程は、故人との思い出を振り返えられる大切な機会です。大切な時間を過ごすためにも、遺品整理は時間が許す限り、心の準備が整ってから行いましょう。そうすれば遺品整理を終えたときには、新たな気持ちで前を向いて進む力が得られるはずです。
スムーズに遺品整理を進めるためにも、ぜひ計画的に取り組み、必要に応じて遺品整理業者の活用も検討してみてくださいね。