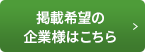【これが現実】孤独死とは?孤立死との違いや対策について(もしもに備えられる)
2025.02.25

- 一人暮らしの親が孤独死してしまわないか不安…
- 孤独死と孤立死の違いを詳しく知りたい
- どんな対策を取れば、孤独死を防げるのか教えてほしい
こんな悩みにお答えします。
歳を重ね、社会とのつながりが薄れると、孤独死や孤立死の恐れが高まると言われています。一人暮らしの高齢者だけでなく、その家族にとっても孤独死は現実的で深刻な問題です。悲しい思いをしないためにも、現場を把握し、しっかり対策しておくことが重要です。
そこで、この記事では以下の内容をお伝えします。
- 孤独死の定義や現状
- 孤独死と孤立死の違いについて
- 親族が孤独死したときの5つの流れ
- 遺族にかかる3つの負担とは
- 孤独死を防げる5つの対策
この記事を読むことで、孤独死の基礎知識や予防方法を具体的に理解し、今すぐ取り組める対策を見つけることができます。
ほんの些細な行動が未来を変えるきっかけになることは珍しくありません。
孤独死に対する不安を解消し、大切な人とのつながりを守りましょう。
孤独死とは?定義や現状について
孤独死とは、主に一人暮らしの人が孤立した状態で亡くなることを指します。
「第6回孤独死現状レポート」(一般社団法人日本少額短期保険協会孤独死対策委員会 2021年6月)によれば、死亡時の平均年齢は61.6歳であり、65歳未満者の割合は50%を超えています。また、20代、30代、40代の男女合計でも20%を超えています。
厚生労働省の調査によると、孤独死のケースは増加傾向にあり、その背景には核家族化や地域コミュニティとの希薄さが影響しています。近年、特に高齢者による孤独死が社会問題として取り上げられています。
現状、孤独死が発見されるまでには平均18日かかり、約4割は3日以内に行われることが多いと言われています。
そのため、高齢者や障害者が住む場所では、孤独死を防ぐための対策が急務となっています。社会全体での理解とつながりが求められる時代です。
孤独死の主な死因は『病気』
孤独死に至る主な原因は病気が多く、特に心筋梗塞や脳卒中などの突発的な疾病が頻繁に見られます。
高齢者や持病を持つ方が、孤立した状態で急に具合が悪くなること、そのまま孤独死につながるケースが少なくありません。日本の統計では、病死が孤独死の要因として約65%を占めているというデータもあります。
また、死亡原因としての自殺も無視できません。特に20歳〜30歳の年齢層での割合が高く、女性に多い特徴があります。
多くの場合、孤独感や社会的な孤立が心理的なプレッシャーを増幅させ、結果として自殺へとつながっています。病気だけでなく、精神的な健康を保つことも孤独死対策には重要なのです。
孤独死発見までは『平均18日』
孤独死が発見されるまでの平均日数は約18日とされています。この期間、高齢者が周囲に何の変化も気づかれずに亡くなっている状況は非常に多く、発見が遅れる要因の一つとなっています。
たとえば、音信不通になった場合、近親者が訪問することによって初めて異変に気づくというケースが一般的です。
多くの孤独死、特に高齢者においては発見の遅れが遺族や周囲の人々にも大きな影響を及ぼします。早期発見ができるかどうかは、周囲の人々の気付きや連絡を密にすることにかかっています。
また、高齢者が住む地域におけるサポート体制の強化も非常に重要です。見守りサービスや地域コミュニティの活動が活発であれば、孤独死のリスクを減らし、発見までの時間を短縮する可能性が高まります。
約4割の孤独死が『3日以内』に発見される
孤独死の約4割は亡くなってから3日以内に発見されるというデータがあります。
この短期間に発見されたケースの多くは、近隣住民や親族からの訪問によって明らかになっています。つまり、連絡を取り合っている状態や、周囲に目を配っている人がいることが重要です。
早期発見がなされることで、必要な手続きや状況の整理が円滑に進む可能性があります。
また、周囲の人々が留意し、声をかけ合うことで、孤独死のリスクも減少します。地域における見守り活動の重要性を再認識する必要があるでしょう。
一人暮らしの高齢者に潜むリスク
一人暮らしの高齢者には、さまざまなリスクが潜んでいます。
特に、健康問題や事故、孤独によって生じる精神的なストレスが大きな要因となります。同居者がいない場合、病気や怪我をした際の急なサポートが得られないため、事態が深刻化する可能性も高くなるのです。
また、孤独感が強まることで、うつ病や認知症のリスクが増加し、日常生活にも影響を及ぼすことがあります。日常の活動が制限される中で、食事や健康管理をおろそかにすることも懸念されます。
次第にセルフネグレクトと呼ばれる状態に陥ることも少なくありません。
このような状況に対処するためには、同居することや定期的に友人や家族と連絡を取ることが重要です。さらに、地域の支援サービスや交流の場を活用し、孤独を和らげ、安心できる生活を維持してあげることが重要になります。

孤立死との違いは『社会的なつながり』の有無
孤独死と孤立死は、いずれも他人の目に触れずに亡くなるという共通点がありますが、その定義と本質は明確に異なります。
孤独死とは、基本的に独居の環境で生活しながらも、家族や友人などの一定の社会的つながりを持つ状態で起こる死亡を指します。
一方で孤立死とは、社会的なつながりがほとんどなく、家庭や地域との関わりが著しく薄い状況下で亡くなることを意味します。この点が、孤独死と孤立死を区別する上で重要な定義となります。
孤立死の場合、家庭や地域社会との交流がほとんど見られないため、亡くなった事実が長期間にわたり発見されないことが少なくありません。実際、孤立死に至る人々は、他者との交わりが極めて少なく、地域社会から孤立しているため、その死が発見されるまで時間がかかる傾向があります。
このように孤独死と孤立死の違いは、社会的つながりの有無が大きく関係しています。
親族が孤独死したときの5つの流れ
孤独死が発生した際には、遺族や親族はさまざまな手続きを行う必要があります。
そのプロセスでは、精神的なショックや悲しみを抱えながらも、遺品整理や部屋の清掃、行政への届け出や相続手続きなど、いくつもの重要なステップを進めなければなりません。
遺族にとっては負担の大きい作業ですが、適切な対応を行うことで、事後のトラブルを防ぐことができます。
それぞれ順に解説します。
➀遺体の発見
孤独死の場合、発見が遅れることが問題となることがあります。
孤独死は、近親者や友人と連絡が取れなくなったことに心配を感じた人が訪問したり、部屋から漂う異臭や周囲環境の異変に気付くことで発見へつながるケースが多くあります。
ですので、早期発見がされることで遺族への精神的・経済的な負担が軽減される可能性があります。
遺体が迅速に見つかることは、孤独死に関連する社会的課題を軽減するためにも重要な要素となっています。
②警察による現場検証・遺族への連絡
遺体が発見された場合、第一発見者は警察へ連絡し、現場に赴いた警察により死因や状況が詳しく調査されます。
この際、現場検証が終わるまで遺族が安易に現場に立ち入ることはできません。特に孤独死のようなケースでは、死因の特定や状況の確認が慎重に行われるため、時間がかかることもあります。
警察の調査の結果、異常がないと判断され次第、遺族に連絡がされます。
しかし、このような突然の知らせは家族にとって大きな心理的負担となり得るため、慎重な対応が求められます。
③遺体の引き取り・葬儀
現場検証が完了した後、遺体は遺族が選んだ葬儀社に引き取られます。
特に孤独死の場合、遺体が発見されるまでに時間が経過しているケースもありますが、そのような場合でも葬儀社がプロとして適切に対応し、必要な手続きをサポートしてくれます。
葬儀社は、普通の形式や家族葬など、さまざまな葬儀プランに対応しており、遺族の希望や故人の意向に基づいて葬儀の形式や場所、日程を決定します。
④特殊清掃
遺体の発見後、特殊清掃が必要な場合があります。
特に孤独死が発生した場合、遺体発見まで時間が経過していることが多く、その間に体液や臭気が部屋全体に広がり、環境が深刻に汚染されてしまうケースがあります。
このような状況では通常の清掃では十分な対処が難しく、専門知識を持つ特殊清掃業者による対応が不可欠です。
特殊清掃業者は、遺体が発見された場所だけでなく、体液や汚染が及んだ箇所も徹底的に洗浄・消毒し、衛生的な状態に戻します。
⑤遺品整理
遺品整理とは、故人が生前に使用していた品々や部屋を整理する大切なプロセスです。
故人の所有物を分類し、不要なものを処分するだけでなく、故人との思い出を整理する場となるでしょう。
感情が揺れ動く瞬間も多いですが、一つひとつ整理を進めることで、心の整理も少しずつできるようになります。遺品整理は、遺族が故人との最後のつながりを実感する場ともいえ、慎重かつ丁寧に進めることが重要です。
このように、遺品整理とは単なる片付けではなく、心や思い出を整理する過程でもあります。
遺族にかかる3つの負担とは
孤独死を経験した遺族は、さまざまな負担を抱えることになります。
その中でも、特に精神的、金銭的、時間的な負担が大きいと言われています。
孤独死の場合、突然の事態に直面することで、遺族は大きな精神的ショックを受けることが一般的です。また、遺品整理や清掃の手配、物件の契約解除など、多岐にわたる手続きが必要となり、それに伴う金銭的支出も避けられません。さらに、これらの対応には時間がかかることが多く、遺族の生活や仕事に大きな影響を及ぼす場合もあります。
こうした負担は、遺族にとって非常に厳しい現実を突きつけるものとなるため、孤独死への事前の準備や周囲との関係の見直しが重要とされています。
➀精神的な負担
孤独死の知らせは、遺族にとって非常に衝撃的なものであり、精神的な負担を大きくします。
愛する人を突然失うことで、悲しみやショックが心を圧迫し、日常生活に支障をきたすことが少なくありません。また、亡くなったことに対する後悔や自責の念も生じることがあります。
特に、孤独死の場合は、長期間連絡が取れなかったことが心の痛みを増す要因になります。
必要に応じて周囲の人や専門機関との連携を強化し、サポートを受けることで精神的な負担を軽減することができるでしょう。
②金銭的な負担
孤独死が発生すると、さまざまな費用が発生します。
葬儀の手配や遺体引き取り、特殊清掃、遺品整理だけでなく、孤独死が起きた部屋の修繕にも費用がかかる場合があります。これらの手続きに伴い、多くの金銭的な負担が生じるため、経済状況に大きな影響を与えることもあります。
遺族の負担を軽減するためには、事前に葬儀社を選び、見積もりを依頼することで予算計画を立てておく方法があります。また、行政や地域の制度などによる公的な支援制度を活用することで、費用負担を抑えられるケースもあります。
事前の対策により経済的な不安を減らし、孤独死後の対応に備えることが重要です。
③時間的な負担
孤独死が起こると、遺族には多岐にわたる手続きが求められ、その一連の過程が大きな時間的な負担を引き起こします。
遺体の発見後から始まる葬儀の手配や遺品整理などは、一つ一つが時間を要する作業であり、これらを短期間で終わらせなければならない状況では、精神的な疲労が一層増してしまうことがあります。その結果、日常生活や他の仕事に支障をきたす場合も少なくありません。
こうした負担を軽減するためには、手続きを家族間で分担することが有効です。また、地域のサポートグループや孤独死の事例にくわしい専門業者、相談機関に助けを求めることも時間管理を効率化しストレスを和らげる手段となります。
遺族自身が1人で抱え込むのではなく、周囲の力を活用しながら対応する姿勢が重要です。

孤独死を防げる5つの対策
孤独死を防ぐためにできる対策として、次の5つを参考にしてみてください。
- ①保険に加入しておく
- ②定期的に連絡取れる環境を整える
- ③社会的な交流を増やす
- ④老人ホームやヘルパーを活用する
- ⑤終活をしておく
これらの日常生活における小さな工夫が、将来的なリスクを減少させる効果を持つことが分かっているからです。
日常から少しずつ準備を進めることで、リスクを大幅に減らせます。
ぜひ、できることから取り組んでみましょう。
①保険に加入しておく
孤独死の際には、葬儀や遺品整理など多くの手続きが必要となります。これに備えて、生命保険や葬儀保険に加入しておく方法があります。
保険を利用することで、死亡時の金銭的負担を軽減し、残された家族への経済的な心配を和らげることが可能になるからです。また、孤独死発見後の手続きをスムーズに進めるためにも役立ちます。
保険の契約を行う際には、将来の状況をしっかり考慮し、慎重に選ぶことが大切です。特に、具体的な保障内容や受取人を明確に設定しておくことで、受け取りに関する思わぬトラブルを未然に防ぐことができます。
孤独死発見時に備えた保険の準備を通じて、自身も周囲の人々も安心できる環境を整えておくことをおすすめします。
②定期的に連絡取れる環境を整える
周囲とのコミュニケーションを重視することも孤独死対策の一環です。
親族や友人と定期的な連絡をとる環境を整えておくことで、普段の様子を把握しやすくなるからです。特に高齢者の場合、体調に異変があった際に気づいてもらえる可能性が高まります。
電話やメールなど、直感的に連絡が取れる手段を利用し、定期的に声をかけたり訪問したりすることが重要です。こうしたやり取りが、心のつながりを強化し、孤立感を軽減する助けとなります。
③社会的な交流を増やす
地域のイベントや趣味の集まりに参加することで、社会的な交流を増やすことも孤独死対策に効果的です。
同じ趣味や興味を持つ人々との交流が、新たな人間関係を築くきっかけとなります。
交流があることで、孤独感の緩和だけでなく、日常生活における支援の機会も増えます。
地域コミュニティの一員として活動することは、精神的な安定をもたらすことにもつながります。
④老人ホームやヘルパーを活用する
高齢者が一人暮らしをする際には、老人ホームや訪問介護サービスも視野に入れましょう。
介護施設やヘルパーの存在が、安全面と精神的なサポートにつながるからです。
体調不良やその他の緊急時にも、迅速に対応できる体制を整えられます。
⑤終活をしておく
終活は、人生の最終段階を見据えて準備を行うことを意味します。
たとえば、遺言やエンディングノートの作成は、自身の考えや意向を整理し、残される家族に負担をかけないための効果的な方法です。
これらを活用して、具体的な希望を明示しておくことで、葬儀の内容や遺品整理の方向性も明確にできます。
終活をしておけば、自分自身の人生を振り返ることができ、充実感を持って今を生きることにもつながります。
高齢者の孤独死に備えるサービスもうまく活用しよう!
高齢者の孤独死を防ぐには、さまざまなサービスが活用できます。
特に、効果的なサービスとして見守りサービスが挙げられます。このサービスは、高齢者の様子を定期的に確認する仕組みであり、異変があった際には早期対応が可能な体制を整えています。具体的には、電話や訪問を通じて健康状態や日常生活における問題の確認が行われ、このプロセスによって孤独感を和らげるとともに、サポート体制の強化にも寄与します。
さらに、安否確認サービスの進化も見逃せません。現在では、IT技術を駆使したセンサー型のサービスも普及しており、高齢者の生活状況をリアルタイムでモニタリングできます。こうしたシステムは、異常の際に迅速な対応を促し、万が一の場合でも安心感を高めてくれます。
また、公的機関である地域包括支援センターも、大切な役割を果たしています。こうしたセンターでは相談窓口を設け、必要な情報やサービスを提供しています。高齢者のための孤独死予防に必要な手続きや対策をしっかりと理解し、準備を進めることができます。
このように、高齢者の孤独死を防ぐには適切なサービスを選び、積極的に利用する意識が重要です。これにより、孤立感の解消や生活の安全性が高まり、自立した充実した生活をサポートできます。
自分自身あるいは家族の状況に合わせて必要なサポートを選択し、日常の中で取り入れることが、高齢者の命を守る重要なステップとなります。
まとめ
今回は孤独死の現状とその対策について解説しました。
孤独死とは、主に一人暮らしの人が孤立した状態で亡くなることを指します。孤独死は高齢者に限らず、人生を孤立して過ごす人々にも起こり得る深刻な問題です。しかし、適切な対策を講じることで、そのリスクを大きく減らすことができます。
孤独死を未然に防ぐために日常生活の中でできる対策として、次の5つを参考にしてみてください。
- ①保険に加入しておく
- ②定期的に連絡取れる環境を整える
- ③社会的な交流を増やす
- ④老人ホームやヘルパーを活用する
- ⑤終活をしておく
特に、家族や地域社会のサポート体制が重要です。周囲の人が普段から見守りやコミュニケーションを意識し、支え合う関係を築くことで、安全で安心できる環境が生まれます。
人によっては「誰かに頼るのは申し訳ない」と感じる方も少なくありませんが、地域や家庭での助け合いは誰にとっても必要な要素です。
孤独死防止は、決して困難な課題ではありません。
些細な行動や早めの準備が、豊かで安心な生活を実現する大きな一歩になります。ぜひできることから始めてみてください。それが、あなた自身の安心にも、そして周囲の人々の安心感にもつながります。
社会全体が支え合い、つながることで、暮らしやすい未来をつくりましょう。