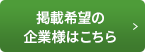遺品整理を49日前からしても問題ない理由(実は故人にメリットあり)
2024.12.04

- 遺品整理って49日前にしてもバチ当たりじゃない?
- 遺品整理は早くはじめた方がいいって聞いたけど、ほんと?
- 49日前に遺品整理するメリットや注意点が知りたい
こんな悩みにお答えします。
「四十九日の法要も終わっていないのに遺品整理するなんて、故人に対して失礼じゃないの?」と感じる方は多いかと思います。
とはいえ、故人の死後はやることが多いため、少しでも遺品整理を進めたい気持ちもありますよね。
結論から言うと、49日前に遺品整理を進めてもまったく問題はありません。むしろさまざまなメリットがあります。
本記事でわかることは以下のとおりです。
- 遺品整理を49日前からしても問題ない理由
- 遺品整理を49日前にする5つのメリットと注意点
- かんたん5ステップで遺品整理を進める方法
- 遺品整理をスムーズにする3つのコツ
- 四十九日の法要が終わるまでにしてはいけないこと
本記事を読めば、故人に感謝の気持ちを伝えつつ、納得感のあるスムーズな遺品整理ができますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
遺品整理を49日前からしても問題ない理由(実は故人にメリットあり)
遺品整理を49日前からすることは宗教的にも法律的にも問題なく、何か不吉なことが起こるわけでもありません。
そもそも仏教の教えでは死後49日間で故人の魂は成仏し、生まれ変わるとされますが、遺品整理を禁止するものではないからです。
むしろ、故人にとってのメリットがあるんです。
その理由は『初七日』と『四十九日』の法要の目的にあります。
| 法要名 | どんな日? | 目的 |
|---|---|---|
| 初七日の法要 | 故人が三途の川のほとりに到着する日 | 故人が穏やかな流れで川を渡れるように祈りを捧げる |
| 四十九日の法要 | 来世の行き先が決まり、旅立つ日 | 故人が極楽浄土に行けるように供養する |
つまり、四十九日の法要までに遺品整理すると、故人が心残りなくあの世へ旅立てる『準備』をしてあげられるからです。
また、遺族にとっても故人との思い出を振り返り、心の整理をしつつ、新たな生活のスタートをきるきっかけになります。
他にもさまざまなメリットがありますので、次項で深掘りしていきます。
遺品整理を49日前にする5つのメリット
遺品整理を早くはじめると、さまざまなリスクやトラブルを回避でき、遺品整理を効率的に進められます。
遺品整理を49日前にするメリットは、以下の5つです。
- メリット①:心の整理ができる
- メリット②:スムーズに形見分けできる
- メリット③:金銭的な負担を軽くできる
- メリット④:親族トラブルを回避できる
- メリット⑤:忌引き休暇で遺品整理できる
それぞれ順番に解説していきます。
メリット①:心の整理ができる
遺品整理をして故人との思い出に触れると、悲しみを少しずつ受け入れられるようになります。
喪失感が和らぎ、不安が軽減されるなど、遺品整理は気持ちを切り替える役割を果たしてくれるからです。
むしろ、時間が経過するほど故人の遺品への思い入れは強くなる傾向があります。故人が亡くなった後は各種手続きに追われるため、先延ばしにするほど心が落ち着かなくなることも。
実際、少しずつでも遺品整理を早くはじめることで、気持ちが前向きになり、新たな生活を送るきっかけになった方も多くいます。
メリット②:スムーズに形見分けできる
遺品整理を49日前にはじめると、スムーズに形見分けができます。
なぜなら、四十九日の法要には故人と親しい親族が集まるからです。
四十九日の法要までに遺品を分けておけば、
- 一度に形見分けがしやすい
- 遠くに住んでいる親戚にも手渡せる
- 遺品の処分についても相談しやすい
思い出を共有しながら、故人と過ごした時間を振り返られるというメリットもあります。
気持ちよく形見分けをするためにも、誰に何を渡すかを決めておき、事前にメンテナンスやクリーニングをしておきましょう。
形見分けについてもっとくわしく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
>>> 【丸わかり】形見と遺品の違いとは?形見分けのポイントや注意点も徹底解説</あ>
メリット③:金銭的な負担を軽くできる
遺品整理を49日前にはじめれば、以下のような支出を削減できます。
- 故人が住んでいた物件の家賃
- 故人のサブスクリプションサービスなどの月額利用料
- 相続税の申告漏れによる延滞税などの支払い
故人の住まいが賃貸だった場合、遺品整理が終わらない限り家賃がかかり続けます。積み重なった家賃を、誰が払うかで揉めるケースはよくあります。持ち家も所有し続けると、固定資産税などがかかり続けます。
故人が契約したサブスクリプションサービスなどは発見しづらく、ダラダラ支払いが継続することも。
相続税の申告が必要なケースでは、故人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内に申告や納税を済まさなければなりません。間に合わなければ延滞税などの支払リスクに見舞われます。
このように遺品整理は早ければ早いほど、支払リスクを軽くするメリットがあります。
メリット④:親族トラブルを回避できる
遺品をそのままにしておくと、親族が勝手に処分したり、持ち出したりするリスクがあるからです。
実例ですが、こっそり高価なものを持ち出して、売ってお金にしようとするトラブルも発生しています。
また、遺品整理を早くはじめるほど遺言書やエンディングノートを早期に発見でき、遺産の分配についてゆっくり話し合えるでしょう。貴金属や骨董品などの高価なものは、今後の扱い方で意見が分かれがちなので、なおさらです。
このように親族間でのトラブルをなるべく回避できるメリットがあります。
メリット⑤:忌引き休暇で遺品整理できる
まとまった休暇をフル活用して、遺品整理を進められるからです。
一般的に民間企業では、故人との関係性が深いほど10日間や7日間の忌引き休暇が与えられます。
平日に作業できるため、役所や業者との手続きもスムーズに進められ、忙しい人でもスムーズに遺品整理を進める機会になるでしょう。
とはいえ、いくら時間があっても、ひとりでの作業だと限界があります。
ですので、忌引き休暇にあわせて親族にも遺品整理に協力してもらいましょう。より効率的に遺品整理を進められますよ。

49日前に遺品整理をはじめるときの5つの注意点
メリットがわかったところで、以下の5つの注意点もしっかり押さえておきましょう。
- 注意点①:親族の承諾を得る
- 注意点②:大切なものを捨てないように注意する
- 注意点③:相続放棄ができなくなる可能性がある
- 注意点④:近所迷惑にならないように注意する
- 注意点⑤:気持ちの整理がついてからにする
さまざまなトラブルやリスクを防止できますので、必ずチェックしておきましょう。
注意点①:親族の承諾を得る
49日前に遺品整理をするときは、必ず親族の承諾を得ておきましょう。
なぜなら、以下のような悪い印象を与えかねないからです。
- 「故人を偲ぶ気持ちが感じられない!」
- 「故人の遺品を大切にしようとしていない!」
- 「価値のある遺品を持ち出したのでは?」
49日前に遺品整理をはじめるときは、前もって親族にその旨を伝えておきましょう。
注意点②:大切なものを捨てないように注意する
事前に捨ててはいけない遺品を把握しておきましょう。
捨ててはいけない遺品は下表のとおりです。
|
絶対に捨ててはいけないもの |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遺言書・エンディングノート | 5 | 土地・不動産などの権利関係書類 | 9 | 年金手帳 | 13 | 鍵 |
| 2 | 現金 | 6 | 通帳 | 10 | 仕事に関する書類 | 14 | 価値のあるもの |
| 3 | 有価証券・保険証券 | 7 | 印鑑 | 11 | レンタル品 | 15 | 故人宛の手紙や郵便物 |
| 4 | ローンの明細 | 8 | 身分証明書 | 12 | デジタル遺品 | 16 | 思い出の品 |
たとえば、書類を紛失すると再発行には時間がかかり、高価なものを捨てると親族間で揉めるリスクがあるからです。
また、あなたにとって必要でなくても、家族にとっては大切にしておきたい遺品もあるでしょう。処分に迷うときは、ひとりで決めずに家族と相談することをおすすめします。
うっかり捨てて後悔しないように、以下の記事でも対策しておきましょう。
>>> 【完全網羅】遺品整理で『絶対に』捨ててはいけないもの16選!注意点もあわせて解説
注意点③:相続放棄ができなくなる可能性がある
一度でも故人の財産に手をつけると、『単純承認』とみなされて相続放棄ができなくなるリスクがあるからです。
49日前に限った話ではありませんが、安易に遺品を処分したり、使用したりするのは避けましょう。
たとえば、資産価値のある財産に手をつけたことで相続意思があるとみなされ、そのときは知らなかった多額の借金を背負うハメになることも。
相続はプラスの財産だけでなく、故人の借金などマイナスの財産も対象になります。
とはいえ、「冷蔵庫の中身や生ゴミはどうしたらいいの?」と疑問に感じる方もいるでしょう。
あくまで金銭的な価値がある遺品が対象になりますので、家庭ゴミなどは処分してしまっても問題ありません。
注意点④:近所迷惑にならないように注意する
騒音で近隣に迷惑がかからないように注意しましょう。
以下のように、思っている以上に遺品整理では大きな音が発生するからです。
- 遺品整理の作業にともなう音
- 不用品を搬出する作業者の出入り
- 早朝や深夜における人の話し声
忌引き休暇などで時間があるからといって、近所迷惑になるような時間帯での作業は御法度です。
故人の死後はやることがたくさんありますので、近隣トラブルに時間を割かれないようにしっかり配慮しておきましょう。
注意点⑤:気持ちの整理がついてからにする
故人が亡くなった後は、悲しい気持ちでいっぱいなのは当然です。そんな中、故人との思い出の品に向き合うのは心理的負担も大きくなります。
遺品整理を49日前に進めるメリットは多々ありますが、気持ちが整理できていない状態だと判断ミスにつながりやすいため注意が必要です。
誤って大切なものを捨ててしまうと、取り返しのつかない事態になることも。
どうしても遺品整理を急ぐ事情があるときは、心理カウンセリングを活用するのも手段のひとつです。
後悔しないように、遺品整理は気持ちの整理がある程度ついてからにしましょう。
【かんたん5ステップ】遺品整理を行う方法
「メリットも注意点もわかった。ところで、遺品整理はどうやって進めればいいの?」という声にお答えします。
以下の5ステップで進めれば、スムーズに遺品整理できますよ。
- ステップ①:全体像を把握する
- ステップ②:ゴールを決める
- ステップ③:遺品を仕分ける
- ステップ④:遺品を処分する
- ステップ⑤:清掃を行う
より具体的な手順が知りたい方は、以下の記事も確認してみてくださいね。
>>> 【具体的7ステップ】遺品整理は自分でできる!コツや注意点も徹底解説
ステップ①:全体像を把握する
まずは遺品整理する現場に足を運んで、全体像を把握しましょう。
遺品の量や大きさ、家の周辺環境を知ることで、これから『何を』『どれくらい』『誰と』すればいいかがわかります。
家族とともに遺品整理をする場合は、一緒に現場を下見しておくとよりスムーズに進められます。目で確かめておけば、遺品整理に必要な道具もスムーズに揃えられるでしょう。
とはいえ、孤独死した現場やゴミ屋敷などの遺品整理は避けましょう。
感染症リスクや遺品整理を完遂できないリスクが高くなるため、遺品整理業者や特殊清掃業者への依頼をおすすめします。
ステップ②:ゴールを決める
いつまでに遺品整理を終わらせるか?というゴールを決めましょう。
ゴールを設ければ作業にメリハリが生まれ、遺品整理をスムーズに進められるからです。
忌引き休暇で遺品整理を進めるときは、いかに計画的に進められるかが肝心です。
具体的には、遺品整理に参加できる家族のスケジュールを把握のうえ、「今日は玄関、明日リビング、明後日はお風呂とトイレ」などの順番を決めます。
故人の住まいが賃貸だと家賃がかかり続けるため、決めたゴールから逆算して計画を立てましょう。必要に応じて遺品整理業者への依頼も視野に入れましょう。
想定外の時間や労力を踏まえたゆとりのある計画を立て、ゴールの達成を積み重ねる意識が大切です。
ステップ③:遺品を仕分ける
スムーズに仕分けるために、以下のルールで遺品を仕分けていきましょう。
- 【必要なもの】思い出の品や形見
- 【必要なもの】貴重品や重要書類
- 【不必要なもの】再利用できるもの
- 【不必要なもの】処分するもの
判断に迷うものは保留にし、ひと通り終えてから判断します。
後になって「勝手に捨てた!」と言われないように、できるだけ家族とともに仕分けましょう。
ステップ④:遺品を処分する
必要なものは保管したり、形見分けしたりして親族で共有しましょう。
不必要なものは、以下の方法で処分しましょう。
- お寺や神社などで遺品供養する
- リサイクルショップやフリマアプリで売る
- NPOや学校などに寄付・寄贈する
- 自治体で処分してもらう
- 遺品整理業者に買取・処分してもらう
お得に遺品を処分するためにも、再利用できるものは使い続けるか、売却するのが賢明です。
なお、家庭ゴミは燃えるゴミや燃えないゴミなどに分別し、自治体のルールに従って処分します。
大量のゴミや粗大ゴミがある場合は、遺品整理業者への依頼もおすすめです。費用はかかりますが、時間をかけずに負担なく、まとめて不用品を処分できますよ。
ステップ⑤:清掃を行う
遺品整理が終わったら、きちんと清掃しておきましょう。
賃貸であれば原状回復させる必要がありますし、持ち家は清掃しておくことで老朽化などを防げます。
なお、賃貸や売却予定の物件は、どこまで清掃が必要かを確認しておきましょう。
場合によっては、「そのままで結構です」ということもあるからです。
遺品整理をスムーズにする3つのコツ
人によっては遺品整理を急がなければならない事情もあるでしょう。
遺品整理をスムーズに進めるには、以下の3つのコツを取り入れましょう。
- コツ①:複数人で作業する
- コツ②:重要書類や貴重品を先に探す
- コツ③:遺品整理業者に依頼する
ぜひ実践してみてください。
コツ①:複数人で作業する
遺族を巻き込んで、複数人で作業しましょう。
もちろん知識やスキルがあるのは当然ですが、遺品整理業者がスムーズに作業できるのはスタッフの数にも注力できるからです。
以下のように、複数人で作業するメリットはたくさんあります。
- 作業効率が上がる
- 肉体的な疲れを軽くできる
- 精神的なサポートが受けられる
- 遺品整理を挫折するリスクが減る
- 誤って貴重品などを処分するリスクが減る
故人との思い出を振り返りながら作業すると、遺品整理そのものが遺族にとっても大切な時間になるでしょう。
コツ②:重要書類や貴重品を先に探す
必要なものを先に抜き取るイメージです。
特に、遺言書やエンディングノートは先に探しましょう。
というのも、故人の意向を確認できるため、遺品整理がはかどるからです。
先に大切なものを探しておけば、誤って処分するリスクを防げますし、遺品処分もよりスムーズに進められます。
遺族にとって意味のある遺品も先に探して残しておきましょう。
コツ③:遺品整理業者に依頼する
とにかくスムーズに進めるなら、遺品整理業者に頼むのがベストです。
遺品整理のプロとして培った経験やスキルを活かし、遺品の捜索から処分、買取、清掃までオールインワンで対応してくれます。
特に、以下のようなケースは遺品整理業者への依頼をおすすめします。
- 孤独死の現場など特殊清掃が必要なケース
- ゴミ屋敷のように大量のゴミが溢れかえっているケース
- なるべく早く遺品整理を終わらせる必要があるケース
また、自治体で処分できない以下のような家電4品目などの処分・買取にも対応してくれます。
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・乾燥機
このような重い家電・家具を家の中から運び出してくれるのもうれしいポイント。
作業料金はかかりますが、すべての作業を丸投げできるため、ほぼ見てるだけで遺品を片付けることができますよ。
悪い業者を選ばないための対策は、以下の記事を参考にしてみてください。
>>> 【トラブルを事前に防ぐ!】遺品整理でやばい業者の5つの特徴と対策
四十九日の法要が終わるまでにしてはいけないこと
一般的に四十九日の法要が終わるまでしてはいけないことは、以下の5つです。
- ①新年の挨拶
- ②お祝い事への参加
- ③お祭りへの参加
- ④お中元やお歳暮
- ⑤引越しや家の新築
もちろんあなたの信仰する宗教によっては問題ないケースもあるでしょう。
そんなときは家族や友人など、「周囲の人がどう感じるか?」という視点を持ちましょう。
周囲と関係がギスギスしないためにも、ひとつずつ確認してみてください。
①新年の挨拶
年始の挨拶や新年会への出席は控えましょう。
「あけましておめでとうございます」には、1年間を無事に過ごし、新年を迎えられたことを祝う意味合いがあるからです。
ですので、年始の挨拶は「今年もよろしくお願いします」や「昨年はお世話になりました」などのフレーズにするとよいでしょう。お年玉はポチ袋ではなく、封筒に入れて「お小遣い」として渡すと問題ありません。
また、年賀状の受付は12月15日くらいからはじまるため、12月初旬までに到着するように喪中ハガキを出しておきましょう。
②お祝い事への参加
可能な限り、結婚式や七五三などのお祝い事への参加は控えましょう。
結婚式の延期は難しいケースもあると思いますが、親族と相談のうえ延期について判断しましょう。結婚式への参加は避けるのが無難です。
ただし、入籍するのはマナー違反になりません。
お祝いの場に穢れを持ち込むことになるため、七五三も日程を変えるのが無難です。
数え年のタイミングで忌中と重なる場合、満年齢の考えに基づき次年度にスライドするのもありですよ。食事会も忌明け後にスライドするのが無難です。
③お祭りへの参加
神様に感謝を伝える儀式であるため、お祭りへの参加は避けましょう。
神道では死を穢れと捉える背景があり、忌明け前に鳥居をくぐることは、穢れを運び込むことを意味するからです。
ですので、神社へのお参りも同じ考え方になります。
とはいえ、神社や地域によっては鳥居の前でのお祈りが認められているケースもあるため、住んでいる地域のルールを確認しておきましょう。
④お中元やお歳暮
お中元やお歳暮も控えましょう。
なぜなら、「穢れを移す」と考える方もいるからです。
縁起が悪いと感じさせないために、『暑中御見舞』や『残暑御見舞』などとしてタイミングをずらして贈るのがしきたりです。
⑤旅行や引越し
可能な限り、旅行や引越しも控えましょう。
旅先へ穢れを移してしまうと考えられているからです。一緒に旅行する人もよく思わない可能性もあるため注意が必要です。
また、故人が旅立っていない四十九日の法要までは、故人の魂が家にいると考えられています。
故人を家に置き去りにしてしまわないように、引越しも延期するのが無難です。
遺品整理についてよくある質問
形見分けは49日前でもできますか?
まったく問題ありません。
形見分けは故人の遺品を大切に引き継ぐ行為であり、故人への敬意の表れでもあります。
49日前に遺品整理していれば、法要のときに親族が集まったタイミングで形見分けでき、遠方まで赴いて遺品を渡す手間を省けるため一石二鳥です。
遺品供養は49日前にしてもいいですか?
遺品整理を49日前からはじめても問題ないように、遺品供養も問題ありません。
むしろ早い段階で遺品を供養してあげると、故人も四十九日の法要のときに心置きなく極楽浄土への旅立ちを迎えられるでしょう。
とはいえ、信仰する宗教や家庭の事情、地域の風習によって事情はさまざまですので、事前に確認しておきましょう。
故人のコレクション品はすぐに処分してもいいですか?注意点は?
すぐに処分しても問題ありませんが、注意点があります。
コレクション品に価値があるケースでは、相続財産になる可能性に注意しましょう。
また、あなたにとっては不要でも、家族にとっては必要なケースもあります。コレクション品の場合、売ればとんでもない値がつくケースも。
価値がありそうなコレクション品は、処分する前に家族に相談したり、専門家に鑑定してもらってから処分しましょう。
遺品整理はいつからはじめる人が多いですか?
四十九日の法要が終わってからや、お盆以降にはじめる方が8割です。
決まりはありませんが、よくあるタイミングは以下のとおりです。
- 葬儀後すぐ
- 諸手続きが終わった後
- 四十九日を迎えた後
- 相続税の発生前
- 親族が集まるタイミング
気持ち的に無理に進める必要はありませんが、期限がある手続きなどを把握したうえで、家族と相談しながら進めましょう。
遺品整理のタイミングは、以下の記事でも深掘りして解説しています。
>>> 遺品整理はいつから始めるのがベスト?―遺品整理をするポイントも解説―
まとめ【49日前の遺品整理はみんなにとってメリットが多い】
結論、遺品整理は49日前にはじめても問題ありません。
むしろ、以下のように多くのメリットがあります。
- メリット①:心の整理ができる
- メリット②:スムーズに形見分けできる
- メリット③:金銭的な負担を軽くできる
- メリット④:親族トラブルを回避できる
- メリット⑤:忌引き休暇で遺品整理できる
遺品整理を早いタイミングではじめるときは、トラブルやリスクを避けるためにも以下の点に注意しておきましょう。
- 注意点①:親族の承諾を得る
- 注意点②:大切なものを捨てないように注意する
- 注意点③:相続放棄ができなくなる可能性がある
- 注意点④:近所迷惑にならないように注意する
- 注意点⑤:気持ちの整理がついてからにする
なお、以下のように遺品整理を急がなければならない方は、遺品整理業者の活用をおすすめします。
- 形見分けが遅れて親族に迷惑をかけたくない
- 仕事や家事が忙しくて遺品整理する時間がない
- 故人の住まいが孤独死の現場やゴミ屋敷だった
デメリットは料金がかかる点ですが、肉体的・精神的な負担をかけずにスピーディーに遺品整理を終えられるメリットがあるからです。
オモイデではお近くの優良業者トップ5の見積もりを無料でお渡ししております。まずは相談だけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせくださいね。