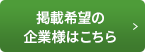お焚き上げとは?料金っていくら?費用相場や依頼先について解説
2025.02.26

- お焚き上げの料金がどれくらいかかるのか分からない
- どこに依頼すれば良いのか迷っている
- 供養の意義や正しい手順を知りたい
こんな悩みにお答えします。
あなたは大切な思い出の詰まった品物や故人の遺品、役割を終えたお札・お守りをどう扱うべきか悩んだことはありませんか?
特に、お焚き上げは日本ならではの文化であるため、初めて依頼する際は疑問や不安があるかもしれません。そこで、この記事ではお焚き上げの基本情報や費用相場など、知っておきたいポイントをすっきりと解説します。
この記事でわかることは、以下のとおりです。
- お焚き上げとは?その意味と背景
- お焚き上げの料金相場と支払い方法
- 安心して依頼できるお焚き上げの依頼先の選び方
お焚き上げについての基礎知識から具体的な依頼方法まで詳しく解説しています。
ぜひ、最後までお読みいただき、悩みを解消してくださいね。
【基礎知識】お焚き上げとは?
お焚き上げとは、主に日本の神道や仏教において重要な儀式の一つで、役目を終えた物品や神聖な物を適切に処分するために行われます。
この儀式では、それまで大切に扱われてきた物を天に還すと同時に、無事に感謝の思いを伝えることが目的とされています。
一般的には神社やお寺などの神聖な場所で執り行われ、神職や僧侶が祈祷や読経を行い、火を使って物品を浄化します。火は浄化の象徴とされ、この過程で物に宿る思いや霊魂を清めると同時に、新たな始まりを象徴するものとも考えられます。
お焚き上げとは、物に込められた感謝や敬意を形にする大切な儀式なのです。
お焚き上げの意味・目的
主な目的の一つは、使われなくなった物を神仏に返すことです。
特にお札やお守りなどは神聖なものであり、一度手にしたらただのゴミとして扱うことはできません。お焚き上げを通じてそれらを丁寧に供養し、本来の役割を終えた物への気持ちを込めて感謝を示します。
また、故人の遺品をお焚き上げする際も、思い出や感謝の気持ちを込めて故人へ返す意義があり、心を整理する重要な過程とされています。物品に込められた人々の心や思いを浄化することで、新たな気持ちで未来を迎える準備ができると考えられています。
さらに、お焚き上げは悪縁を断ち切る手段としても利用され、過去のしがらみを清め、新たな一歩を踏み出すための精神的な区切りをつける役割も果たします。
お焚き上げの起源・背景
お焚き上げという習慣は古くから日本に根付いており、平安時代から始まったその歴史は、宮中の神事や火祭りに由来しています。
古代より火は浄化の象徴とされており、庭燎や左義長などの行事が現在のお焚き上げに発展してきました。
これらの行事では、火を使って物品を焼くことで、その品物に宿っていた魂や思いを清め、再び神聖な場所へ還すために行われてきました。
また、お焚き上げの際に用いられる初穂などの神聖な供物は、神への感謝や祈願を込めて捧げられるもので、火を通してその思いを天に届ける役割を果たしています。
お焚き上げは日本の文化や宗教と深く結びついている、重要な儀式の一つとして今日まで受け継がれています。

お焚き上げできる4つの依頼先と費用相場
お焚き上げを依頼する際は、以下の4つの選択肢を検討してみてください。
- ①神社・お寺
- ②葬儀社
- ③遺品整理業者
- ④お焚き上げ専門業者
大切なのは、ニーズに合わせた選択です。
それぞれの特徴を理解したうえで、自身の希望や状況に合った方法を選びましょう。
①神社・お寺
神社や寺は、伝統的なお焚き上げを行う場所として広く知られています。
費用は品物の種類や大きさによって異なりますが、一般的には0円から15,000円程度が相場とされています。お焚き上げを依頼する場合、希望する物を神社や寺に持参し、神職や僧侶に依頼します。
持参する物については、可燃物や一般的に不要になった物であることが求められます。品物に感謝と敬意を込めて供養する儀式であるため、形式を整えることが重要です。
お焚き上げを依頼するときは神社や寺の指示に従い、スムーズに供養してもらいましょう。
②葬儀社
葬儀社もお焚き上げの依頼先の一つです。主に故人の遺品を対象にした供養を行います。
お焚き上げには、故人の思い出の品や個人が大切にしていた物を一緒に供養することが含まれます。葬儀社が行う場合、トータルなサービスが受けられるため、遺族にとっても便利です。
料金については、葬儀社によって異なりますが、一般的に数万円の範囲になることが多いです。
遺品整理と併せて依頼する場合、パッケージ料金として提供されることもあります。これにより、手間を省きつつ、適切な供養を行える点に魅力があります。
③遺品整理業者
遺品整理業者も、お焚き上げができる依頼先の一つです。
最近では、遺品整理を専門とする業者が増えており、物品の整理だけでなく、供養も同時に行うことができるサービスが提供されています。これらの業者は神社やお寺と連携しているため、手続きの煩わしさを軽減しつつ、必要な供養をスムーズに行えるメリットがあります。
料金は業者によって異なるため、相場としては3,000円から70,000円程度と幅があります。
依頼する際には、事前に複数の業者から相見積もりを取って確認しましょう。また、特定の品物を焚き上げるオプションが用意されていることもあります。
希望に応じた柔軟な対応が期待できるため、気になることは事前に確認してみると良いでしょう。
④お焚き上げ専門業者
お焚き上げ専門業者は、お焚き上げを専門とするサービスを提供しており、依頼者のニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。
料金は物品の大きさや種類に応じて異なり、小さなものであれば1,000円〜5,000円ほどが一般的です。大きな物品に関しては一括料金が適用される場合も多く見られます。総じて、遺品整理業者と同じく3,000円から70,000円程度と考えておきましょう。
大切なのは、事前にどれくらいの費用がかかるかをきちんと調べること。いずれの方法を選択するにしても必須の心構えとなりますので、安心して依頼するためにも必ず実践するようにしましょう。
お焚き上げが必要な場面とは
お焚き上げは以下のように、物品の処分や供養が必要なさまざまな状況で実施されます。
- ①神棚や仏壇・仏具などを処分するとき
- ②季節の飾り物などを処分するとき
- ③故人の遺品整理をするとき
- ④愛用品を手放すとき
それぞれの場面において、なぜお焚き上げが必要とされるのかを見ていきます。
①神棚や仏壇・仏具などを処分するとき
神棚や仏壇、仏具といった品々は、特別な思い入れを持たれる方が多く、信仰の対象として尊重されるものです。
このような品物は不用になったからといって、無造作に廃棄するのは気持ちの面でも適切ではありません。
ですので、お焚き上げや焚き上げという儀式を通じて、物に宿る魂を丁寧に供養し、感謝の気持ちを込めて神仏への敬意を示すことが重要です。
特に、神棚や仏壇は家庭内で家族を守る存在として長く親しまれてきたことが多いため、新しい環境への移行や交換の際には慎重な対応が求められます。
②季節の飾り物などを処分するとき
季節の飾り物は、年中行事や特別な時期に使用され、使い終えた後には適切な方法で処分することが大切です。
特に、お正月に飾る正月飾りや節句飾りなどは、その象徴的な意味合いから、ただ廃棄するだけでなく、物に込められた思いや意味を尊重するための対応が求められます。
正月飾りを処分する習慣として、日本各地で伝統行事である「どんど焼き」が行われています。正月飾りを地域単位で集め、大きな焚き火を焚いて燃やし、歳神様を天に送り届ける儀式です。神々に感謝を伝えるとともに、自身や家族の幸福と健康を祈ることできます。
神社を訪れる際には、不要になったお守りやお札も一緒に持参するとよいでしょう。
③故人の遺品整理をするとき
故人の遺品整理が行われる際には、思い出の詰まった品物が多く現れるため、遺族にとって心の整理が必要な時期となります。
物を手放すことは非常に難しいことですが、大切に保管されてきた遺品については、感謝の意を込めて行うお焚き上げがおすすめです。故人への祈りをささげ、その思いを新たにする大切な機会とできるからです。
神社・お寺や専門の業者にてお焚き上げを依頼すれば、故人への感謝を深めるとともに、遺族自身も新たな一歩を踏み出す準備につながります。
遺品整理の際には、品物の背景や大切な思いを尊重しながら対応することを心がけましょう。
④愛用品を手放すとき
長年つき合ってきた愛用品や思い出の品を手放す際には、さまざまな感情が交わるかと思います。
その物には、多くの思いが詰まっているため、ただ捨てるのは心苦しいものです。ですが、お焚き上げなら、これらの物品に感謝の気持ちを込めて手放せます。
物に込められた思いを供養することで、これまでの大切な時間に敬意を払い、次のステップに進むための心の整理ができるからです。
お焚き上げをすることで、愛用品の処分がより意味深い体験となるでしょう。
⑤引っ越しなど生活環境が変わるとき
新しい生活環境へ移る際は、不要な物を整理し、新たなスタートに備えることが重要です。
特に、神棚や仏壇、そして季節の飾り物など、生活に密接に関連した物については、単なる処分ではなく「お焚き上げ」を行うことが推奨されます。
お焚き上げは、これまで大切にしてきた物への感謝の気持ちを表し、古い家から新しい家へと思いをつなげる大切な役目を果たしてくれるからです。
単に物を捨てるだけではなく、心を込めてお焚き上げを行えば、清らかな気持ちで新しい生活をスタートできます。
このような丁寧なアプローチは、より心穏やかで充実した未来を築く第一歩になるでしょう。

お焚き上げできる品物
お焚き上げは、特定の種類の品物に対して行われる供養の儀式です。
主に神仏に関わるものや故人に関連する品、さらには思い出のある私物などが対象となります。
これらの品々には物に宿る魂があるとされ、それを浄化するとともに感謝の気持ちを込めて適切に処分することが大切です。
お焚き上げできる代表的な品物について、順に紹介します。
神棚や仏壇・仏具
神棚や仏壇、仏具は、宗教的な意味が強い特別な品物です。
これらの品々は、家庭内で神や仏を祀る際に使用され、多くの人々にとって大切な存在となっています。神棚に納められるお札もまた、神社から授かり、家庭で祀ることで加護を得る大切なものです。
不要になった神棚や仏具を単に捨てるのではなく、神仏に対する感謝の意を込めてお焚き上げや返納を行いましょう。
たとえば、古いお札や破損した仏具は、神社や専門の場所に預けて焚き上げることで、正しい形で神仏と向き合えます。特に、長年家族を見守り続けてきた神棚や仏具自体には、多くの思い出や願いが宿っています。
これらを適切に供養することで、物に宿っていた魂や思いを天に還し、新たな開始を迎えることができるのです。
正月飾りなどの季節の飾り物
正月飾りや節句飾りなどの季節の品々も、お焚き上げの対象となります。
お正月の飾り物は、新年を迎えた際に歳神様を迎え入れ、感謝の意を表す重要な役割を果たします。
そのため、行事が終わった後にはそのまま捨てるのではなく、お焚き上げやどんど焼きといった伝統的な方法で丁寧に処分しましょう。
お札・お守り
お札やお守りは、人々が信仰の対象として持つ品です。
これらは特に神社や寺院で授与され、その場での祈願が込められていますので、単に捨てるわけにはいきません。お焚き上げにより適切に供養することにより、神聖なものとしての意味合いが守られるのです。
一般的には、使わなくなったお札やお守りは神社に持参して返納しましょう。
人形・ぬいぐるみ
子ども時代の思い出が詰まった人形やぬいぐるみとは、長い間寄り添ってきた特別な存在であり、多くの場合、それらには深い愛着や気持ちが込められています。
そのため、単に処分することが難しく、お焚き上げという形で供養することをおすすめします。
人形供養祭などを開催している神社や寺院も多く、こうした行事に参加すれば、愛用品をきちんと供養できるでしょう。
人形やぬいぐるみを感謝の気持ちとともに手放すことは、単なる処分以上に価値ある過程です。思い出を整理し、新たな一歩を踏み出すためにも、お焚き上げを利用するのは有意義な選択と言えるでしょう。
手紙・写真
手紙や写真には、封筒ごとその時々の思い出や愛情が込められており、これらを処分する際には慎重な配慮が求められます。
特に、故人からの手紙や特別な思い出の詰まった写真をただ捨てるのは心が痛むため、そうした場合に「お焚き上げ」が重要な役割を果たします。
お焚き上げとは、物や手紙、写真、さらには封筒に宿る感情やメッセージを焚き上げの火によって清めて供養し、新しいスタートを切るためきっかけとなります。
過去を受け入れ、物を手放すことは、心の整理や精神的な成長にもつながる大切な過程とされています。
お焚き上げを通じて、物に込められた思いを丁寧に見送り、新たな未来への一歩を踏み出しましょう。
お焚き上げできない品物
お焚き上げは、神聖な儀式として特定の品物を供養するための方法ですが、全ての物が対象となるわけではありません。
特に、法的または倫理的な理由からお焚き上げできない物品がいくつか存在します。
これらについて知識を深めておきましょう。
電化製品
電化製品は、お焚き上げの対象には適していません。
一般的に、これらは可燃性の材料を含んでおり、安全に燃やすことができないため、環境への影響も懸念されます。電化製品には貴重な金属やプラスチックなど、多くの異素材が使用されており、それぞれの取り扱いが求められます。
特に、家電4品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫や冷凍庫、洗濯機や乾燥機)やパソコンなどの小型家電は、法律に基づいた適切な処分が求められます。
したがって、不要になった電化製品は、リサイクルや専門の廃棄業者に依頼して処分しましょう。
各自治体のルールを確認し、正しい方法で処分することが望ましいと言えます。
危険物や有害物質を放つ物
危険物や有害物質を含む物品も、お焚き上げの対象外です。
たとえば、化学薬品やガスボンベ、バッテリーなどが該当します。これらの物を火で焚き上げることは非常に危険であり、周囲の人々や環境に悪影響を及ぼす可能性が高いため、取り扱いや処分には厳重な注意が必要です。
適切な処分方法は、専門の業者に依頼するか、正しい廃棄施設を利用しましょう。
地域の指示やルールを遵守し、安全に対処することが求められます。
食品
食べ物に関しては、通常お焚き上げで処分はしません。
なぜなら、食品は生物的な性質を持ち、腐敗や害虫発生の原因となるため、不適切な処分方法は周囲に悪影響を及ぼす可能性があるからです。
破棄する場合は、指定された方法に従い、地域のごみ回収ルールに従いましょう。
特に、賞味期限切れの食品や残った料理などは、コンポストや生ごみ処理機を利用するなどして、有効的に処分することが勧められています。
食品を廃棄する際は、責任のある処理を心がけましょう。
生き物
生き物およびペットの遺体もお焚き上げの対象外です。
ペットの遺体を適切に処理するためには、動物霊園や専門の動物火葬業者への依頼を検討しましょう。
これによりペットの尊厳を守りつつ、適切な供養ができるでしょう。
動物の飼い主としての責任を果たし、生き物の命を大切にすることが求められます。
のし袋や書き方の正しいマナー
お焚き上げを依頼する際には、のし袋や表書きの書き方のマナーを知っておきましょう。
神社やお寺への依頼は、神聖な行為として扱われるため、正しいルールやしっかりとした礼儀が求められるからです。
これらの正しい方法を理解し実践すれば、感謝の気持ちを丁寧に伝えられ、良い印象を与えるきっかけにもなります。
水引きのない白い封筒を用意する
使用する封筒は、水引きのない白い封筒を用意しましょう。
封筒を選ぶ際には、紙質や色合いにも注意を払い、清潔感のあるものを選択しましょう。
封筒にはお焚き上げの際に入れる金額を収めることが多いため、その金額に見合ったサイズの封筒を選ぶことが重要です。金額が直接相手へ適切に伝わらないよう、失礼に当たらない配慮が求められます。
封筒とは形式的であってもお焚き上げの行事においては慎重に選ぶ必要があるアイテムといえますので、準備を進める際にはこれらの点をしっかり考慮しておきましょう。
【神社】表書きは「玉串料」「初穂料」「御焚上料」と書く
神社にお焚き上げを依頼する場合、表書きには「玉串料」「初穂料」「御焚上料」と記載します。
これらの表現は、日本の神道における重要な用語であり、お焚き上げの目的や意義を明確に反映しています。それぞれの書き方には意味があり、行事の内容や趣旨に応じて適切に使い分けることが大切です。
お金を包む際には新札を使用し、できるだけきれいな状態で用意すると良いでしょう。また、表書きには丁寧に書き方を整え、誤字や汚れがないよう心がけましょう。
【お寺】表書きは「お布施」と書く
お寺でお焚き上げを依頼する際は、表書きに「お布施」と記入します。
この表現は、仏教における供養やお礼の気持ちを示すためのもので、心からの感謝を表す大切な言葉とされています。
お布施は、僧侶に支払う金銭の意味を持つため、書き方にも丁寧さが求められます。すべての文字はしっかりとした筆跡で書き、両手で渡すことで、心を込めた敬意を表せるでしょう。
お守りの返納方法と注意点
お守りは、その年の間に守護していただいた感謝の気持ちを込めて、使用後に返納することが推奨されています。
返納の際には、神社や寺院などの適切な場所に収めることが基本であるため、事前に確認しておきましょう。
返納する際のマナーと手順
お守りを返納する際には、まずお守りに宿っていただいたご利益や守護に対して感謝の気持ちを忘れずに持つことが大切です。
返納は、その年の終わりや新しい年の始まりに行うのが一般的ですが、都合に合わせていつでも行って問題ありません。重要なのは、神社やお寺に直接足を運び、誠意を持って返納を行うことです。
返納手続きを行う際は、お守りを授与してもらった神社やお寺に伺うのが基本ですが、他の神社や寺院でも返納できます。
現地で指定された場所にお守りを持参し、必要に応じて受付の方に渡します。その際、特別な言葉を発する必要はありませんが、心の中で「ありがとうございました」と感謝の念を込めると良いでしょう。
また、場合によっては郵送での返納を受け付けている神社やお寺もあります。たとえ直接お参りが難しい場合でも、事前にしっかり確認をし、お守りを丁寧に取り扱う心構えを大切にしましょう。
お守りを返納することは、神社やお寺とのご縁を尊重する行為でもあります。誠意を込めて正しい手順で行うことで、次の新たなご利益をいただく準備にもつながります。
お焚き上げができない場合の代替方法
お焚き上げが困難な場合、物品を適切に供養するための代替方法も知っておきましょう。
自然環境や空間の制約、または個人の信仰や宗教的な理由によって、お焚き上げを行えないという状況も少なくありません。
そのようなときには、自分の気持ちを込めて丁寧に物品と向き合うことを心がけながら、取り入れやすい代替方法を試してみましょう。
適切な手段を選ぶことは、感謝の気持ちを表現し、物品に込められた想いを尊重する一助となります。
塩でのお清め方法
塩を用いたお清めは、古くから日本において行われてきた伝統的な方法です。
塩には浄化の力があるとされ、物の持つ悪影響を取り除くために使われています。
具体的には、処分したい品物を白い紙や布に置き、塩を振りかけて供養します。この際、塩を振りかけるだけではなく、心を込めて感謝の言葉を唱えることが大切です。
浄化した品物は、他のゴミとは分けてゴミ袋に入れて自治体の処分方法に従って処分しましょう。
自宅で行える供養の方法
自宅で手軽に供養を行う方法もあり、亡くなった方の思い出の品や愛用していた物を供養する際には、家の中で落ち着いた気持ちで向き合える場所を選ぶことが大切です。
自宅内に小さな供養スペースを設け、そこに物品を置いて手を合わせたり、感謝の気持ちを言葉にして伝えたりすることで、自然と心に安らぎが生まれます。
さらに、手作りの供養状や仏像などを飾ることで、さらに思いを込めた供養が可能です。無理のない範囲で、自分の気持ちを形にしながら、毎日少しずつ静かな時間を過ごすことで、物品への思いを丁寧に整理しつつ供養を進めることができます。
このような方法により、亡くなった方や物品に対する気持ちを一層深める機会となるでしょう。
まとめ
今回はお焚き上げの費用相場や依頼先について解説しました。
お焚き上げは、長く使用した物や思い出深い品々に感謝を込めて供養する、日本独特の文化的な儀式です。この行為を通じて、不要になった物を正しい方法で処分するだけでなく、自分自身の心を整理することもできます。
依頼する際は、以下の4つの依頼先を検討してみましょう。
- ①神社・お寺
- ②葬儀社
- ③遺品整理業者
- ④お焚き上げ専門業者
お焚き上げを行う際には、物品の取り扱いに注意し、感謝の気持ちを持つようにしましょう。これにより、新たなスペースが生まれ、生活環境が整いやすくなります。
また、物を手放すことは、過去への感謝と決別を示し、新しい一歩を踏み出すための重要なプロセスでもあります。そのため、「捨てる」だけではなく、「供養する」という意識を持つことが、心の平安を得る助けにもなるでしょう。
お焚き上げのマナーや手続きについて理解を深められると、先人たちが大切にしてきた伝統を継承する意義も感じられます。さらに、地域とのつながりを深める機会としても、お焚き上げは役立ちます。
神社やお寺での現地参加を通じて地域の行事に関わることで、新たなつながりを生むきっかけにもなるでしょう。
心を込めた供養は物との良好な関係を保ちながら、次のステージへ進む準備を整えてくれるため、より充実した日常を手に入れられるようになります。
ぜひこの機会にお焚き上げについて再確認し、大切な物に感謝をしながら供養を行ってみてください。
きっと心の中の整理や、新しいスタートへのきっかけを得られるでしょう。